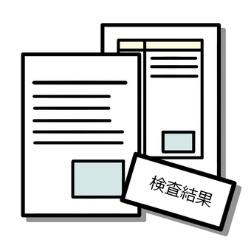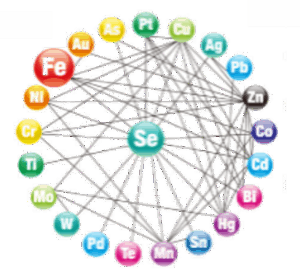こんにちは。今泉栄養療法クリニックです。
9月の第44回「ココロとからだセミナー」では 「血液データの読み方 初級編①」 をテーマに、分子栄養学的な視点から血液検査を深読みする方法についてお話しました。
基準値と「健康値」の違い
一般的な健康診断の血液検査では「基準値」が示されますが、これはあくまで「検査会社の職員(自称健康者)」の平均値にすぎません。
生活習慣が乱れていたり慢性的な疲労を抱えていても、病気と診断されなければ「健康」とされるのです。
私たちが重視するのは、体の機能を最適に保つための 「健康値」。これは生化学的根拠と臨床経験をもとにした、より実用的な目安です。
自律神経と白血球の関係
心と体はつながっており、自律神経のバランスは白血球の分画(血液像ともいい、白血球の種類ごとの割合の事)から推測できます。
- 好中球+単球:リンパ球の比率が およそ60:30 であることが理想。
- ストレスが強いと好中球が増え、リラックス状態ではリンパ球が増える傾向があります。
実際の症例では、交感神経が優位な方、副交感神経が優位な方、小児特有のリンパ球優位の例などを紹介し、それに関連して、ポリヴェーガル理論にも少しふれました。
タンパク質不足のサイン
血液中の 総蛋白・アルブミンは血清中の蛋白質を直背う測定したものですが、ここは、よほどのタンパク不足でなければ低下しません。その他、尿素窒素(BUN)・肝酵素(AST/ALT/γ-GTP)・LDLコレステロール などが、体内のタンパク質状態をより早く反映します。
タンパク質は酵素やホルモン、細胞膜の材料になるため、不足すると体全体の機能が低下します。
実際に30代女性の症例では、総蛋白やアルブミンが低く、コレステロールも不足しており、かなりのタンパク不足が疑われた30代女性の例をご紹介しました。
コレステロールの本当の役割
「コレステロールは低ければ安心」と思われがちですが、実は違います。
コレステロールはその役80%が胆汁酸の材料になります。胆汁酸は脂質や脂溶性ビタミンの吸収に不可欠なものです。その他、細胞膜やホルモン、ビタミンD、CoQ10などの大切な材料です。
- 高すぎる場合:甲状腺機能低下や腸内環境の乱れが背景にあることも。
➡胆汁酸分泌低下により材料のコレステロールが余る
➡脂質や脂溶性ビタミンの吸収低下が起こる。 - 低すぎる場合:エネルギー不足やタンパク不足の可能性が高い。
➡胆汁酸、細胞膜やホルモン、ビタミンD、CoQ10などの材料不足
つまり、血清中のコレステロール濃度が「高すぎても低すぎても、組織では不足している」のです。
鉄不足を見抜く
鉄は、酸素を運ぶ赤血球の重要な材料ですが、エネルギー産生、脳機能にもとても重要な働きをする、大切なミネラルです。
鉄不足を判断するには、赤血球数やヘモグロビン値の他、 血清鉄・フェリチン・MCV・TIBC・UIBC などを組み合わせて見る必要があります。
一般の医療機関では、貧血(赤血球数やヘモグロビン値の低下)がなければ、鉄は足りている、と判断されることが多いですが、その前にフェリチン・MCV・TIBC・UIBCの異常が現れ、すでに鉄欠乏の症状が出始めます。つまり、「貧血」は鉄欠乏の末期症状なのです。
症例として紹介した20代女性は、血清鉄16、フェリチン5以下と重度の鉄欠乏状態。
鉄欠乏では、倦怠感や息切れ、頭痛、抜け毛、冷えなどの症状が起きやすくなります。また、情緒が不安定になったり、論理的思考力が低下するなどの症状も現れることがあります。
まとめ
今回のセミナーでは、
- 基準値だけでは見えない「隠れた不調」
- 自律神経のバランスを映す白血球
- タンパク質や鉄不足のサイン
について学びました。血液データを「深読み」することで、体からのSOSを早めにキャッチし、根本的な改善につなげることができます。
次回(10月16日開催予定)の「初級編②」では、肝機能・血糖・甲状腺 について解説します。ご自身の検査データを持参いただくと、さらに理解が深まりますよ!
※ この記事を通じて、「血液データをもっと活用したい」と思われた方は、ぜひ次回のセミナーにもご参加ください